|
2012.08.13 |
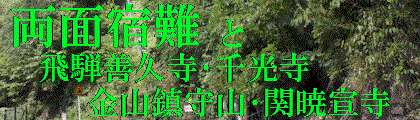 |
岐阜県高山市丹生川町ほか |
岐阜県にお住まいの方で年配の方は一度は耳にされた名前と思われますが、しかし「両面宿儺」とは?
| 両面宿儺(りょうめんすくな)とは
両面宿儺は上古、仁徳天皇の時代に飛騨に現れたとされる異形の人、鬼神である。 では、両面宿儺の歴史的史跡はどんな処にあるのでしょう |
両面宿儺の話が伝説でなく実際の話とする証拠は「日本書紀」にその記述があることです。
|
『日本書紀』仁徳天皇65年の条に両面宿儺が登場する。 (日本書紀原文) (現代語訳) |
飛騨地方の観光地に「飛騨鍾乳洞」の向かいの山の中腹に「1.両面宿儺洞窟」があります。
|
「飛騨大鍾乳洞」上り口 |
その駐車場に「日本一宿儺鍋」があります。
(「飛騨鍾乳洞」へはここを”クリック”)
時価2億円の金塊盗難で有名な飛騨大鍾乳洞駐車場の
|
両面宿儺鍋 岐阜県高山市丹生川町日面1147 |
|
|
これは、土産店裏の山に「両面宿儺洞」があり、地元に残る伝説から「宿儺鍋」が作られ |
鍋の脇には「両面宿儺洞」の看板があります。
|
飛騨大鍾乳洞駐車場の脇山の |
|
山の中腹あたりに洞があります。 |
では両面宿儺と鍋の因縁とは?
|
鍋との因縁 |
|
両面宿儺洞へ行くには |
|
土産物店の並びを裏へ回ります。 |
|
道路脇に登り口の階段と柵があります。 |
|
登り口には洞窟まで登れない方のために「両面宿難遥拝所」があります。 |
|
「鍾乳堂」のご主人が鍵を開けてくれて、洞内の電灯の電源を入れてくれます。 |
 |
|
両面宿儺洞窟(画像は岐阜県丹生川村企画観光課発行より) |
|
出発 |
| 両面宿儺の伝説 (岐阜県丹生川村企画観光課発行) 日本古代史の中で耶馬台国から草創期の、謎の4世紀とされる時期があります。 即ち、大和王朝発展期に至る約100年の課程です。 文献的には「古事記」と「日本書紀」に描かれる王権成立と発展の時代であり、大型古墳時代開幕の時でもある。 およそ1、500余年のむかし飛騨にも大和朝廷の力が及び、大八椅命が斐陀国造に任じられています。 飛騨を支配していた両面宿儺は朝廷に従わなかったので仁徳天皇の命令を受けた武振熊(たけふるくま)命が討伐の兵を進めました。(つづく) |
|
少し登ると足場は良くなりますが手摺が頼りになりません。 |
|
10分程登ると鉄製の階段になります。 |
|
|
|
両面宿儺の伝説(その2)岐阜県丹生川村企画観光課発行より |
|
両面宿儺の伝説(その3)岐阜県丹生川村企画観光課発行より |
|
階段を4折れほど登ると落石のため大きな穴が開いています。 |
| 両面宿儺の伝説(その4)岐阜県丹生川村企画観光課発行より 武振熊命一行はやがて前方に一際高く聳え立つ乗鞍岳を仰ぎ、宿儺の居場所の予感を受け、左側の渓流小漢僧谷を目指しました。 宿儺の本拠天然要害の出羽ヶ平両面洞窟を発見し、洞窟を目指して岩山をよじ登り激しい攻防戦がくりひろがりました 50人力宿儺は岩石を投げ落とし、大木を引き抜いて投げつけ、神業のような敏捷さで走り回って戦い続けました。 少人数の宿儺勢次第に疲れ、最後は宿儺と武振熊命の組打ちとなり、岩屋の前で凄い一騎打ちとなりました。 とうとう命に組み伏せられ縛られてしまいました。 宿儺の超人的な能力に感じ入った命は、降伏して従うよう奨めましたが、頑として聞き入れず、やむなく討ち果たしました。(つづく) |
|
地震のための落石が道を塞いでいます。 |
|
両面宿儺の伝説(その5)岐阜県丹生川村企画観光課発行より |
|
登り始めてから20分ほどで洞の入口へ到着します。 |
|
洞入口には村人が「安永三年(1774)」に安置した脇仏があります。 |
|
内部には電灯が点いています |
|
内部も鉄階段が設けてあり電灯が点いています。 |
|
両面宿難は大変な場所に住んでいたのです。 |
|
一番奥へ着いたようです。 |
|
観光客用に原型を壊さず手摺が施設されています。 |
|
腰をかがめ頭を低くして下ります。 |
|
下に駐車場が見えてきてホッと安心しました。 |
次は国道158へ出てすぐ下の両面宿儺の石膳がある寺晋門山 善久寺へ
|
2.晋門山 善久寺 岐阜県高山市丹生川町日面 |
|
宿儺が村人と別れのもてなしを受けた石膳のある善久寺を紹介します。
|
国道158号の丹生川町へ出ると「日面橋」の道標があります。 |
| 日面と両面宿儺 今からおおよそ千六百年前、出羽ヶ平(高山市丹生川町日面地内=以前は大野郡丹生川村日面)の岸壁(がんぺき)から身の丈、一丈八寸、一体両面四手両脚の宿儺が、身には甲冑を着して、兵杖を帯び、、二手には斧を持ち、一方の手に印を結んで出現したと伝えられています。 飛騨・美濃の広い地域には宿儺が十一面観音の化身として、国家安泰五穀豊穣を願い民人のために働いた伝説が残されています。 しかし、日本書紀には大和朝廷に従わず、討伐の命を受けた、武振熊(たけふるくま=神功皇后に仕えた将軍)と美濃の高沢山( 岐阜県関市神野山、標高354m)で戦い(「両面宿儺の戦い」)破れたと記されています。 (出典:フリー百科事典ウィキペディアより) |
|
しばらく進むと右側に「両面宿儺の御膳石」の看板が見えてきます。 |
|
其の反対側には「晋門山
善久寺」の看板もあります。 |
|
看板の近くの道を北へ上る道があります。 |
|
100mほど上ると赤い屋根の家が「晋門山 善久寺」です。 |
|
一見普通の家の様ですが「晋門山 善久寺」です。 |
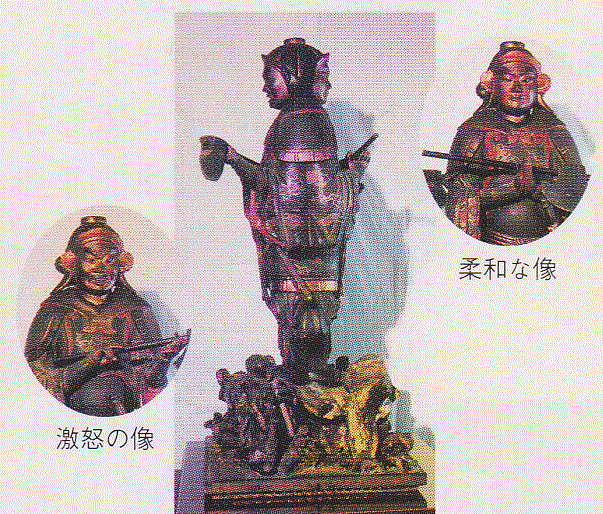 |
|
善久寺所蔵の両面宿難像(作者不明) |
|
ご住職に「御膳石」の案内をお願いすると |
|
「御膳石」は寺の前の石段を下り草道を歩き、もう一段下へ降りると木の下にあります。 |
|
狭い道を下ると右側の木の元に在りました。 |
|
石の上面には食事を盛ったと云われる、窪んだ穴があります。 |
|
自然のままにしてあり、いにしえの時の流れを感じられました。 |
次に宿難が開山と伝えられる千光寺を紹介します。
同じく国道158号の丹生川町下保にあります。
|
3.袈裟山 千光寺 岐阜県高山市丹生川町下保1553 |
|
飛騨国千光寺は、仁徳天皇の御代、今から1600年前に飛騨の豪族両面宿儺(りょうめんすくな)が開山し、
約1200年前に真如親王(弘法大師の十大弟子の一人)が建立したといわれる古刹です。
|
国道158号から北へ入り1kmほどにあります。 |
|
境内は広く、かなり手前の県道脇に石柱があります。 |
|
広い境内に遊歩道が作られています。 |
|
国指定の天然記念物「五本杉」は途中にあります |
|
山門の手前で車を止めます。 |
|
境内を入ると「円空佛収蔵館」があります。 |
|
千光寺は「雲海」で有名! |
|
今は木が大きく育ち視界が悪くなりましたが、天候により今でも素晴らしい「雲海」が見られるそうです。 |
|
「道場」 |
|
高山市指定文化財(建造物) |
|
高山市指定文化財(建造物) |
|
|
|
宿儺堂 |
|
|
|
高山市指定文化財(建造物) 宿儺堂 慶長三年(1598)建立。 当山の開創者「両面宿儺」を祀る堂宇である。 両面宿儺は日本書紀にも登場する飛騨の開拓者であるが、最後は朝廷と戦って敗れる。 平成の解体修理の折にに天井裏から棟札が発見され、慶長三年の建立と判明した。 永禄七(1565)年,武田軍勢の飛騨攻めの際に当山七堂伽藍は焼き討ちに遭い焼失した。 その後文禄一(1592)年に本堂の原型として草庵が建てられた、時の中興初代住職、玄海法印が一千座 の本尊観世音菩薩の修法を行っている。 平成十五年六月十六日指定 高山教育委員会 |
|
|
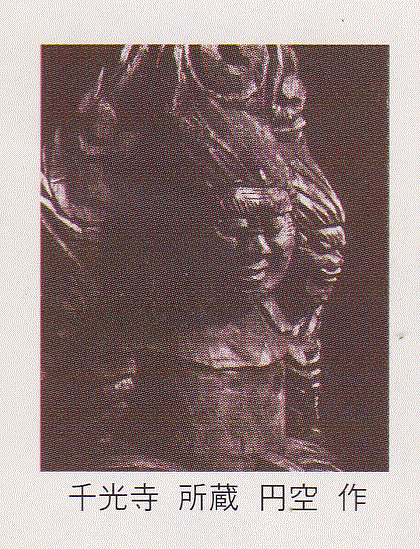 |
|
(画像は岐阜県丹生川村企画観光課発行の「両面宿難洞窟」より) |
|
2013年04月にテレビ愛知放送局で |
|
テレビ愛知の「なんでも鑑定団」より |
| 「日本書紀」と地元の伝承との違い (出典:フリー百科事典ウィキペディアより) 『日本書紀』では皇命に逆らう賊とされる両面宿儺だが、飛騨から美濃にかけての旧飛騨街道沿いには様々な伝承がのこり、その内容は『日本書紀』の記述と異なるものが多い。以下に主な伝承を挙げる。 高山市の伝承 元和七年(1621年)の奥書(典籍のうち写本の巻末に書かれた記載で,主として書写・校合・伝授などについて記す。)を持つ『千光寺記』には、高山市丹生川町下保にある袈裟山千光寺の縁起が記されている。 下呂市金山の伝承 『金山町誌』によれば、武振熊命(たけふるくまのみこと)が討伐に来ることを知った飛騨の豪族両面宿儺は、八賀郷日面出波平を出て金山の鎮守山に37日間留まり、津保の高沢山(岐阜県関市)に進んで立てこもったが、敗れて討死したという。 関市下之保の伝承 『新撰美濃志』に引く大日山日龍峰寺の寺伝では、飛騨国に居た両面四臂の異人が、高沢山の毒龍を制伏したとする。 この他に、両面宿儺を討った武振熊命の建立と伝わる八幡社が飛騨各地にある。 (以上出典:フリー百科事典ウィキペディアより) |
|
弁天堂 |
次に両面宿儺
|
岐阜県高山市・下呂市 |
|
5-1.金山 鎮守山 岐阜県下呂市金山町十王坂 |
|
|
金山鎮守山画像近日掲載予定
|
| 金山鎮守山の由来伝承 仁徳天皇の時代(西暦400年頃)、大和朝廷に従わない両面宿儺(りょうめんすくな)という怪人がいました。 2つの顔と4本の手を持ち、飛騨大野郡八賀郷(現在の飛騨市丹生川町)日面出羽ヶ平の岩窟より、飛行してこの地に杖を休め、37日間大陀羅尼というお経をとなえ、国家安全、五穀豊穣をお祈りした後、大和朝廷の追討の将、難波根子武振熊(なにわのねこたけふるくま)を迎え撃つため、関市武儀町下の保の高沢山へ飛んでいった」という伝説があります。 その後武振熊は高沢で宿儺を破り、宿儺を追って飛騨の入り口であるこの地・金山町中津原に至り大岩の上に八幡様を勧請しました。この岩が「根子岩」と呼ばれ下原八幡神社に残っています。 画像出典:フリー百科事典ウィキペディアより |
|
5-2.下原八幡堂 岐阜県下呂市金山町中津原 |
|
次に岐阜県関市の暁堂寺へ
|
6.金龍山 暁堂寺 岐阜県関市肥田瀬1280 |
|
|
関市と飛騨金山を結ぶ「県道58号」の肥田瀬地区にある。 |
|
山道を上がると駐車場があります。 |
|
金龍山
暁堂寺 (きんりゅうざん ぎょうどうじ) 仁徳天皇の御世、飛騨(斐大、肥田)の国八賀の里の異人「両面宿難」(両面僧都)がこの地に宿営し、一夜、夢枕にたつった金龍のお告げに従って、五穀の豊穣と国土の安穏、住民の和楽を祈願しつつ彫り上げたもの。 (関市重要文化財指定) |
 |
|
開帳期間は毎年4月17日〜24日の9時〜17時です。 |
帰り道 境内の脇に「若?塚」があり
「古老の口伝に斐太の偉人”両面宿儺”の使(?)者
舎人和可の髪を埋奉したと言ふ」
最後に関市下之保に伝わる「両面宿難」伝承を紹介します
|
7.大日山
日龍峰寺 岐阜県関市下之保4585(海抜267m) |
|
| 両面宿儺がこの地方で龍神を退治して建立した寺 岐阜県下最古の寺で、本堂前方が舞台造りで京都の清水寺に似ていることから、美濃清水とも呼ばれています。 鎌倉時代の北条政子寄進の多宝塔は、国の重要文化財に指定されています。 寺伝によれば、5世紀前半の仁徳天皇の時代、美濃国に日本書紀にも登場する両面宿儺(りょうめんすくな)という豪族がいた。 両面宿儺はこの地方に被害を及ぼしていた龍神を退治し、龍神の住んでいたこの山に祠を建立したのが始まりと伝わる。 鎌倉時代、北条政子によって再興されたと伝えられている。 (現地説明板より) |
|
山門をくぐると石段が続く |
|
更に石段は続きます。 |
| 大日山日龍峯寺本堂(本尊:千手観音菩薩) 本堂五間四面入母屋造り桧皮葺で山頂傾斜地の岩上に建立す、前方は舞台造りで京都の清水寺によく似ており、美濃清水の異名で世に知られています。 鎌倉尼将軍寄進の本堂は惜くも応仁文明の乱により戦火の犠牲となり現在の本堂は寛文十年(江戸時代)の建造物です。 (県指定・市指定文化財) |
更に登ると「多宝塔」が見えてきます。
| 多宝塔(国指定重要文化財) 地元の人から、「高澤観音」と親しみを込めて呼ばれている日龍峯寺は、古い歴史を秘めた名刹です。 境内には鎌倉時代、時の尼将軍・北条政子によって建立されたという多宝塔が残されており、国の重要文化財にも指定されています。 |
| 千本桧と高沢山(354m)(天然記念物) 日龍峯寺本堂前の広場中央にあるこの千本桧は、樹高はおよそ20メートル、根元の回りは3メートルを超える巨木で、根元より無数に分かれた枝葉はまさに千本桧の名にふさわしく、霊木として景観をそえています。(市指定天然記念物) |
両面宿儺の伝承のある場所を7箇所紹介してきました。
各地の「日本書紀」の悪人説より、岐阜県下に残る善人説を信じたくなりました。mori70silver