|
2012.05.16 |
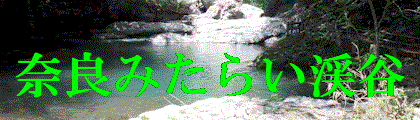 |
奈良県吉野郡天川(てんかわ)村北角 |
エメラルドグリーンに輝く神秘的な淵。大小様々な滝と巨岩を縫い底まで透けて見える清流が流れる「みたらい渓谷」には、
川沿いに遊歩道(近畿自然歩道)が整備され、つり橋からは滝を上から眺めることもでき、まさに絶景の渓谷です。
|
みたらい渓谷の位置 |
 |
|
赤点線が「世界遺産 大峯奥駈道」 画像は「奈良県観光局ならのにぎわいずくり課内」発行の |
「みたらい」の名の由来
後醍醐天皇の皇子、護良親王が勝利祈願に手を清めたとされ、名付けられた渓谷。
大峰山系の山上川に添って奇岩が点在し、紅葉の時期の景観の美しさは有名な渓谷です。
|
「みたらい渓谷」の出発点は急な階段から始まります。 |
|
上には吊り橋が |
|
下には渓谷の渓流が |
|
「みたらい」の名の由来 |
|
上流には、また滝が |
|
みたらい渓谷「哀伝橋」 |
|
「哀 伝 橋」 |
橋の袂でとりあえず昼食を
「哀伝橋」を渡って出発です。
|
谷の上には、また吊り橋が |
幾つもの滝があるが、名前の案内がありません。
|
滝の音だけが静寂を破ります。 |
|
鉄製の遊歩道が続きます。 |
|
崖と渓流の間に作られた遊歩道(近畿自然歩道) |
|
遊歩道は良く整備されていて安心して渡れます。 |
|
「光の滝」 |
「光の滝」を過ぎると急に静かな渓流になります。
「洞川」(どうがわ)温泉まで4.1kmの標識
|
遊歩道(近畿自然歩道)は、しばらく渓流から離れて進みます。 |
渓谷は遥か下のほうへ離れました。
|
|
|
洞川(どろがわ)温泉まで2700kmの標識 |
|
「観音の岸壁」への分岐点標識 |
|
県道21号線 |
遊歩道は一時「県道21号」と合流します。
|
「天川村の大門」 |
|
「吉野熊野国立公園」と「世界遺産」 |
|
「南朝の歴史」を包む観音峰の岩屋 |
|
|
|
歴史ある修験道を「洞川温泉」へ向かいます。 |
やがて洞川温泉近くまで来ました
|
建物は洞川温泉の下流にある「浄化センター」の建物です。 |
洞川温泉近くの修験道脇奥に赤い鳥居と社(やしろ)が見えました。
|
「ダイジョウゴンゲンサン」 |
いよいよ「洞川温泉」です。
修験者の宿・洞川温泉と修験道場・龍泉寺について
 |
| 洞川 (どろがわ)温泉奈良県吉野郡天川村洞川 修験者(大峯信仰)や龍泉寺の隆盛と共に登山基地として栄え、二十数軒の旅館や各種土産物店やお食事処が軒をつらね、温泉街を形づくっています。 歴史を感じる、なつかしい雰囲気のただよう街で、役行者の高弟「後鬼」の子孫の里とも伝えられています。 また、一帯は代表的なカルスト地形(石灰岩台地)で、ごろごろ水に代表されるミネラル分を適度に含むおいしくて体に良い水も湧き、標高820mの名水の山里はいつも賑わいを見せています。 (天川役場観光情報(http//www.vill.tenkawa.nara.jp/sightseeing/data/facilities.htmlより) |
| 龍泉寺 洞川温泉から約600m龍泉寺は真言宗醍醐派の大本山として多くの信者を集めておりますが、洞川から登る修験者は、宗派を問わず龍泉寺に詣で、水行の後、八大龍王に道中安全を祈ってから、山上ヶ岳に向かうしきたりとなっています。 修験道の根本道場として信者・登山者の必ず訪れる霊場です。 (天川役場観光情報より) |
 |
| 今から千三百年の昔、大峯の山々を行場として修行された役行者が、山麓の洞川に憩われたとき、こんこんと湧き出る泉を発見しました。龍の口を名付けて、そのほとりに小堂を建て、八大龍王をお祀りされたと伝えられます。 それが龍泉寺の始まりです。 それから200年後、龍泉寺の1キロ上流の蟷螂の岩屋に雌雄の大蛇が住みつき、修験者たちに危害を加えました。 そのため、一時大峯修行を志す人が絶えて、龍泉寺も荒廃してしまいました。 修験道中興の祖、聖宝・理源大師が、真言の秘法によって岩屋の大蛇を退治し、龍泉寺を再興したと伝えられています。 |
 |
| 龍の口から湧き出る清水は、役行者以来、今も絶えることなく清冽な流れを境内にたたえ、修験者の清めの水として大峯山中第一の水行場となっています。 (画像及び説明文は「天川役場観光情報」http: //www.vill.tenkawa.nara.jp/sightseeing/data/facilities.htmlより) |
感想
みたらい(御手洗)渓谷はさほど大きな渓谷ではないが清流の素晴らしさは一見の価値があります。
遊歩道も整備されており、足元も安全で高低差も少なく快適な散策道でした。